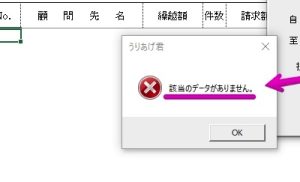点滴スタンドをうまく操縦するにもこつがいる。なぜなら僕のだけキャスターが三つしかついてなかったからだ。でもそれを片手で押して歩くのも随分上手くなった。夕方廊下ですれ違った看護師さんが「まあ、それ交換しましょうか?」と聞いた。僕は「いえ、結構です。これ、気に入ってるので」と答えた。

今何時だろう。九時の消灯から何度か途切れ途切れに眠った。深夜であるのは間違いない。トイレに行って暗い廊下を帰って来る間誰にも会わなかった。看護師詰め所のあたりで僅かに話し声が聞こえただけだった。開け放した病室入口近くのカーテンの隙間から読書灯の明かりがもれている。僕は自分のベッド回りのカーテンを開けながら読書灯の下の男を見た。男は背中に枕を当てて半分体を起こし、片手で500ページはあるだろう分厚い本を支えて読んでいる。僕は点滴チューブが絡まないように気をつけながら自分のベッドに横たわった。昨日より随分良くなっている。
『休息だな。何年かに一度の神様からのプレゼント……』
僕は頭の後ろで腕を組み、あの男が読んでいた本のことを考えた。一瞬見ただけではあるが装釘や本のサイズから見て雑誌や実用書ではない。たぶん小説である。戦国武将の話かな。あるいは長編ミステリー。男と女の話。重くてどこにも行き場をなくした泥のような人生。
あの本の分厚さが彼の入院生活の長さを象徴しているように思えた。僕はたぶんまもなく退院する。そしてまたあの慌ただしくも面白おかしい、情けない人生に戻っていくのだ。
京都のワークショップをなんとかやり終えて僕は4月15日の日曜日に岡山に帰って来た。翌日は昼近くまで寝ていた。間一髪で生き残った兵士のように体中の細胞が睡眠を欲していた。昼になり冷蔵庫をあけたがろくな食材はなかった。前の週にもらった里芋の煮ころがしがあったのでそれを温めてご飯を食べた。体はまだ疲れていたがとにかく元のリズムを取り戻さないといけない。準備期間を含めてワークショップに使った4日間の空白をこれから数日で挽回しないと落ち着かない。次の松江の個展までは一月近くあったが頭の中の進行表には4日遅れ、と警告サインが表示されている。
午後はずっと仕事をした。肩や首が痛くなると立ち上がってみっともない体操のようなことをした。インターネットラジオは20th Century Radioというステーションに固定してある。1940年代から50年代のアメリカのラジオプログラムを延々と流し続けていて、サム・スペードやフィリップ・マーローなどの探偵物が聞ける。
夕方になったが買い物に行く気になれなかったのでハムエッグと冷凍庫のパンを食べた。まるで朝食だがそんなことは気にならない。夜も仕事をしてその夜は僕としては早めにベッドに入った。
翌日午前中は京都から持ち帰った荷物を整理し、洗濯をした。昼になり冷蔵庫を見たがもちろん昨日なかったものが現れたりはしない。『今日こそ買い物に行かないとなあ』と思いながらけっきょく昨日食べ残していた里芋を食べた。
それから二時間後、突然吐き気がした。この数日便秘気味だったのでそのせいだと思っていた腹痛も二段階ほどグレードが上がっている。二度嘔吐しトイレの床に毛布にくるまって悪寒に耐えていた。ちょっとでも寝たらましになるのでは、と思って這うようにベッドに行くのだがすぐにトイレに行きたくなる。それでも夕方近くになって10分ほど寝ただろうか。だが期待も空しく何の良い兆候も現れなかった。
「イテテテテテ……」「アカン、アカン、モウアカン……」情けない独り言を発声しながらひたすら我慢していたが夜になっても状況は変わらない。僕は携帯電話のアドレス帳を開きI君に電話した。「モシモシ、ヤノデス」 「あー、久しぶりです。どうしたんですか?」
「アノナ、ジツハナ……」
こういう事態でもなんとなく僕は切羽詰まった喋り方ができない。
「ま、それでどないしょうかと思って」
I君は症状を聞き出すとすぐに「そこの近くにK病院という病院があります。そこへ行って下さい」と言った。
「個人病院はあかんの」「今閉まってるでしょ」「今すぐ行くんかいな」「すぐに行って下さい。一時間ほどしたら電話して様子を聞きます」
I君は古い友達なのだが今は福山の大きな公立病院の副院長をしている優秀な外科医だ。そんな偉いお医者さんにあんなにきっぱりと言われたら行くしかない。

僕はバッグに財布と保険証を放り込みとにかくよろよろと部屋を出た。車をおいてある所まで50メートルほどなのだがその間何度も立ち止まり、前屈みになって痛みをこらえた。ようやく車にたどり着いた。こんな病人でもキーを回せばエンジンはかかるしアクセルを踏めば動き出す。I君の教えてくれた通りに行くと確かにK病院は1キロも離れていない所にあった。救急外来の受付で書類を書き僕は名前を呼ばれるまで待ち合いのベンチに転がっていた。当直医は若いハンサムな医者だった。レントゲンを撮り症状や病歴を聞いてやはりその医者もきっぱりと言った。
「入院して下さい」
「すぐに?」
「そうです。これから看護師に案内させます」
『お医者さんってみんなこうなのかな。でもこの命令口調は悪くないな。どうします?なんて聞かれても困るし。
ま、いいか。とりあえず今夜安心して眠れる場所が見つかった,ということで』
痛みをこらえながらも頭の中はこんな具合なのである。
明けて水曜日、昨夜からの点滴の薬効か痛みは少し治まっている。雨が降っていた。4階の病室の窓からは正面に灰色の空をバックにしてオレンジ色の巨大なクレーンが見えた。新しい病棟が建つのだろう。カッパを着た数人の男がレゴを組み立てるようにクレーンが移動させた鋼材をボルトで固定していく。
担当医は小柄な中年のドクターだった。
「白血球がおっ!というぐらい増えています。原因はわかりませんがとりあえずしばらく絶食して点滴で様子を見ましょう」
日頃の度を超したへそ曲がりはなりを潜め、僕はできるだけ感じのいい笑顔で「はい」と答えた。
何もすることがないが不思議と退屈でもない。窓の外の降り続ける雨とクレーンのスローな動きを見ていると催眠術にかかったようにまた眠ってしまった。
しばらくして目が覚めた。同じ病室のもう一つのベッドの方で何人かの話し声が聞こえる。友達がお見舞いに来ているのかな、と思ったがどうも仕事の話をしているようだ。内容からして入院している男は建設業を営んでいるらしい。少しいらいらした口調で指示を与えている。見舞客が帰った後もその男は携帯電話で何カ所も電話をして謝ったり脅したりしている。どうも請け負った仕事が自分の足の怪我で納期が遅れていて任せていた職人達も思うようにやってくれていないようだ。口数は多くないがなかなかの迫力である。
午後は長い。
ベッド回りのカーテンを半分ほど開けて廊下を通る人々や窓からの風景、ゆっくりとしぼんでいく点滴バッグをぼんやり眺めていた。
入口脇の男の所に女が来た。水色のジャージの上下にふわふわしたキティちゃんのスリッパ、眉はほとんどなく赤い髪を高い所でポニーテールに括っている。男はまた携帯電話で誰かと低い声で話をしている。その通話が終わると女が男に話を始めた。
「まだ数値が下がらないんだって。下がったらインターフェロン始めるんだって」男は黙っている。
女が語るぽつりぽつりとしたとりとめのない話がカーテン越しに聞こえる。
「ラーメン食べたいなあ」
二人は夫婦のようだ。女は向かいの病室から来たようだった。先に女が入院して、男が怪我をして同じ病院に入院することになったらしい。男は女の話にたまに「う」とか「あ」とか低く短く答えるがほとんど黙っている。何も優しい言葉は交わされていないのに女は嬉しそうだった。
「ラーメン食べたいなあ」
二人とも三十代だろうか。これから長い人生を共に生きていくのだろう。ずっと後になってこの病室の時間を懐かしく思い出すことがあるだろうか。男の仕事は厳しそうだ。怪我の治療も長引きそうだ。女の病気はどうなのだろう。心配の種は尽きない。それでも女は幸せそうだ。

しばらくして二人が病室を出て行くのと入れ違いに中年の看護師が点滴の交換に来た。出て行く二人を見ながら
「仲いいですよねぇ」と言った。
「あんなんなら入院も悪くないな、と思います」
看護師は手際よく作業をしながら笑っている。
夕方になり友人のNが身の回りの物を買ってお見舞いに来てくれた。とにかく何も持たずに深夜出て来たので本当に有り難い。ベッド脇の机の上やロッカーの中にそれらを収めたらなんだかほっとした。
『これで大丈夫』
これも僕の思考回路の一つである。本当は少しも大丈夫ではないのだが事態がほんの僅かでも改善するとこれで大丈夫、と思ってしまう。ま、いいかと大丈夫。これで生きているようなものだ。たぶんグロスマスターKも同じだと思う。今度座右の銘を聞いてみよう。
結局僕は四日目に退院した。担当医のFドクターが三日目の回診で「白血球の数値も平常値に下がっています。二三解せないこともありますがこういうことはよくあることなんです。なんだか解らないけど治ったからまあよし、ということですね。明日にでも退院は可能ですがどうしますか?」
「それなら明日退院させて下さい」
Fドクターは頷きながら立ち上がった。出て行く時に思い出したように言った。
「I先生とはお友達ですか?」
I君が電話をしてくれたようだった。
「そうなんです。昔からの古い友達なんですが病気になった時だけつい頼ってしまいます」
「うん、いいんじゃないですか」
マスクに隠れて口は見えないが目が笑っていた。
僕は退院して今は大変調子がいい。多分絶食というのはいいのだと思う。日頃くたびれ果てている胃も腸も何も仕事がなくなると自分のあるべき姿、生き甲斐を思い出すんじゃないか。
どこも痛いところがなくてトイレに行っても気持ち良くお通じがある。その度に僕はあの雨が降り続いていた四日間を本を読み返すように思い出す。
深夜救急外来のベンチで痛みをこらえて転がっていたこと、その夜明け方まで十数回は行ったトイレのピンクの壁、クロームメッキのドアノブ、夕方になると弁当箱を持ってクレーンからはしごでおりて来た男のカーキ色の作業着、三日目にやっと許可が出て髪を洗った時のシャンプーの匂い、退院の日の朝食に出た重湯の味、そして入口近くのベッドにいた男と日に何度もやって来た女が交わしていた静かな会話。深夜その男が読書灯の下で本を読み続けていたエドワードホッパーの絵のような姿を。