僕のそばにずっと一本のギターがある。かれこれ45年。毎日弾いた時代もあれば何ヶ月も触らない時代もあったがとにかく僕が住んでいるところにはずっとこのギターがあった。
AbeGutというナイロン弦のアコースティックギターで、中学二年になった時に15000円で親に買ってもらった。中学二年というのは人が成長して行く過程で一番厄介な時期である。それを僕は一本のギターでやり過ごすことができたんだな,と思う。そう思うとこのギターはその時その時で僕の恩人であった。

最初に弾けるようになったのはグリーンスリーブスという曲だった。
それからイエスタデイだったかな。
なんとか右手と左手が仲良く音符を追いかけることができるようになった頃中学校でクラス対抗の合唱コンクールみたいな行事があった。僕のクラスは加山雄三の「旅人よ」という曲を歌うことになった。僕のクラスには僕と松本君という二人がギターを弾けたので他のクラスはみんなピアノ伴奏だったけれど二人のギターで伴奏することになった。松本君の方が僕より早くギターを始めていたから上手だった。松本君がアルペジオで、僕がコードストロークで伴奏することになった。そして本番当日、二人でユニゾンでの前奏が終わり歌の伴奏が始まったのだが僕は打ち合わせを無視して僕もアルペジオで最後まで弾いた。理由は明瞭である。アルペジオの方がかっこよかったからだ。
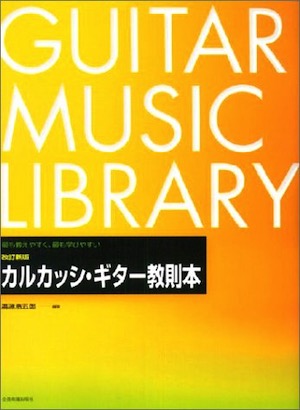
それからしばらくして松本君がクラシックギターの教則本として今でも広く使われているカルカッシという本を貸してくれた。僕はその教則本の一番最後にあった「アルハンブラ宮殿の思いで」という曲から練習を始めた。もちろんその曲はそれまでの数十ページの練習曲を地道にさらえた人がやっと最後に練習すべき曲なのだから弾けるはずがない。でもそのハードルというにもあまりに高過ぎる、足のつりそうな(この場合指か)難曲を一週間ほど必死で練習して半分ほど弾けるようになったところで僕は松本君にその楽譜集を返した。この曲はギター音楽の愛好家でなくとも誰でも一度は聞いたことのある名曲で、親指で分散和音を弾きながら残りの指でメロディーをトレモロで奏でる。特に冒頭のメロディーはこれぞスペインの叙情といった感じの美しい曲なのだがそこが弾けるようになって僕は「もういいや」とやめてしまった。その曲を全部弾けるようになるより早くカルカッシから解放されたかったのだ。
高校生になってからはいろんな楽譜を買い込んで勝手に弾いていたがよく弾いたのは映画音楽だった。「ブーベの恋人」、「鉄道員」、「夜霧のしのびあい」など。
ある日楽器屋で妙な雰囲気の楽譜集を見つけた。それは手書きの楽譜をコピーして製本したような感じで表紙には306とだけ書いてあった。曲はすべてジャズのスタンダードナンバーでどうも海賊出版らしかった。ジャズは中学の時からよく聞いていたが弾くとなるといったいどうやって弾くものやら見当もつかなかったがその楽譜に書いてあるのはメロディーとそれに対応したコードだけの、いわゆるCメロと言われているものだった。あのカルカッシのように弾くべき音がすべて順番に書いてあるのではなくメロディーと和音という最小の情報しかなかった。 「これがジャズなんだ・・・」僕は途方に暮れながらもなんだか嬉しくなった。
僕が手探りしながらあれでもないこれでもない、あれは嫌い、これもちょっと違うと彷徨っていた暗くて細い道のかなたに小さいけれど明確な矢印を見つけたのはその時だったかもしれない。それは単に音楽上の嗜好の問題ではなく、まことにやっかいで手に余る自分という存在をどうすれば収まるべきところに収められるかという命題の根本的な解決方法であった。つまり努力することにためらいを覚えなくていい方向が指し示されたということだ。 振り返ってみれば僕はハードワークへの無意味な羞恥のようなものがあって、頑張らなくてもそれなりにやっていけるならそれでいいや、みたいな嫌らしい自我を振りかざしていた気がする。でもいずれそれが命取りになるだろうこともなんとなく予感していた。そんな人間が生きていける場所はこの世界にはない。少なくともそういう鼻持ちならない人間を誰も好きにはならない。だから恥じずに努力して頑張るには僕向けの場所と方法が必要だったのだ。それは今風に言えば「自分探し」と言えるのかもしれないが僕は自分の中にでなく306という楽譜に見つけた。それはまことに幸運であった。
大学に入って最初に友達になった高橋君はビル・エヴァンスに似ていた。事実彼はピアノを少しだけ弾けた。同じように彼はベースもドラムもギターも少し弾けた。どういう経緯でこんなに何もかも少しだけ弾けるようになったのか少し不思議な気もしたが彼が楽器を弾いている姿はなかなか素敵だった。後に彼は岡山にあったチャイナタウンというキャバレーのビッグバンドでピアニストのアルバイトをしたがそれはピアノの腕を買われてというよりピアノを弾いている姿を買われてらしかった。
とにかく僕は高橋君に連なる人脈でジャズのバンドに入れてもらった。それは一応ジャズ研というサークルに属していたのだがそのサークルには楽器を弾くメンバーと弾かないメンバーに分かれていた。ある時、僕がジャズ研の部室に行くとそのバンドのメンバーがドアの前に立っている。
「矢野、鍵開けて」
僕は変だな、と思いながら鍵を鍵穴につっこんで回そうとしたが回らない。みんな「やはりな」という顔をしている。
「俺たち閉め出されたみたいやな」
どうやらいつのまにか鍵を取り替えられて楽器を弾くメンバーはクビになったようだった。僕達の側から見たら特に問題もなく思えていたのだが反対側から見たら何かしら我慢ならないことがあったのだろう。例えば馬鹿に見えるとか、思索的でないとか、ただうるさいだとか。
まあ確かにそれも頷けたりもするものだから僕達は抗議も争いもせずにクビになってやった。

そしてその後僕の音楽キャリアはなだれうつように、あるいは転げ落ちるように夜のキャバレーバンド時代に入っていくわけだがそのあたりのことは前にも少し書いたのでここには書かない。
実はごく最近僕は東京の市ヶ谷で個展をした。現在の僕はギターとは全く縁のない美術方面のアーティストが職業なのでギターの話やらましてキャバレーバンドの話などあまり公ではしない。特に個展会場ではもの静かで思索的なふりをしているからそれらの話題はタブーである。だが今回はしてしまった。それはSさんという女性のお客さんがいるのだがこの人のする話がやたら面白いのでつい負けじと調子にのっているうちにやってしまったのである。だが有り難いことにSさんは大喜びしてくれた。受けた。
内容的には思わず眉をひそめられてもしょうがないそんな話を面白がってくれたのはもしかしたら彼女が大の落語好きだからかもしれないなあ、と今思う。その推理が当たっているならばとどのつまり僕の人生が落語みたいなものだからなのだろう。この基本姿勢が僕の人生をこんなものにしてしまった。
いささか苦い思いがこみあげないでもないがそれさえもどこか自分で面白がっている風でもある。まことにいい歳になってまだこんな人間であるのは人生に対しての無責任、冒涜と言われてもしょうがないがもうモデルチェンジはきかない。
それはグロスマスターKも同じであろう。もう取り返しなどつくはずはないのである。クソ真面目に仕事をしながらもどこかでオチをつけようと企んでしまういわば性のようなものだ。
「かた」や「けり」をつけるだけでは物足らずいつも「おち」をつけようといらぬ頭を使う。時には身を捨ててまでおちをつける。
もう少しましなものをつければいいのにと我ながらため息をついたりもするのだがおち至上主義は僕の血管に生まれた時から流れているのである。
何か他につけるべきはないのかなあ。例えば利子とか……
そうか、元手がないのにつくはずないね。


